
こんにちは、キャリアカウンセラーのかとうじゅんこです。
「手放しましょう」
悩んだり苦しんだりしているとき、他人からこういったアドバイスを受けたことはないでしょうか。
あなたはそのとおり実行……つまり「手放せ」ましたか?
手放すってどういう意味
「手放しましょう」
私自身は悩んだとき、特にこの言葉に出会うことが多かったように思います。
そして、簡単には手放せませんでした。
そもそも、「手放す」とはどういう意味なのでしょうか。
新選国語辞典(第六版)(小学館)によると次のように解説されています。
①手に持ったものを放す。
②所有物を売ったり、人にあたえたりする。
③自分のそばから放す。「むすこを手放す」
④仕事を中止する。「手放せない仕事がある」
(「新選国語辞典(第六版)」(小学館))
日常でよく使うのは、「自動車を手放す」とか「田畑を手放す」とかといった、
所有しているものを処分などするときかと思います。
これは上記でいうところの特に②に該当しそうですね。
④も日常でよく使うかもしれません。
「今ちょっと手が放せないところだから、あとにして」なんて言ったりします。
①は物理的に「手に持っているものを手から放す」という使いかたのようですが、
この状況だと「手放す」と表現するより
「彼は手に持っていたペンを机に置いた」というような言いかたをすることのほうが日常では多いかもしれません。
③はどうでしょう。
「むすこを手放す」……むすこって、息子のことだと思うのですが、
これは「お婿さんに行かせた」とか「養子に出した」とか、
「都会へ行きたがる息子をやむなく田舎から送り出した」……というようなさまざまな状況が想像できます。
いずれにしても、自分のそばから放すことで、息子はどこかへ離れていくわけです。
悩んだりしたときによく見聞きしアドバイスされる「手放す」は
この③に最も近いようです。
なぜ手放せないのか
先ほどもお伝えしたとおり、悩んだ時、私は簡単には手放せませんでした。
「手放しましょう」というアドバイスは
本や動画で嫌というほど拝見しました。
中でも、まるでお手玉を上空へ放り投げるようなしぐさで「手放しましょう」と繰り返す助言には、
「は?」としか言いようがなかった記憶があります。
私にはわかりづらい助言で、手放すことにはまったく役立ちませんでした。
そもそも、「手放せない」といって困っている人に
「手放しましょう」と180度逆のことを助言しても
あまり効果はないでしょう。
では、なぜ簡単に手放せないのでしょうか。
手放せないのにはシンプルな理由があると思います。
それは、手放さないことについて「何かしらの肯定的な意図があるから」です。

大切なものって、どう扱う?
手放せないということは、あなたにとって何かしらの肯定的な意図があるのです。
あなたは肯定的な意図を持つものを、お手玉のように放ることができますか?
普通はしませんし、できないと思います。
人は意味あるもの、価値あるものを投げたりしません。
落として壊してしまったり、汚してしまったり、
それによって捨てる羽目になるかもしれません。
落としてしまった拍子に、何かに紛れて見失ってしまい、
二度と手元に戻ってこなくなるかもしれません。
むしろ大事に大事に懐にしまっておいて、時には取り出して眺め、また懐にしまうでしょう。
手放せないものは、あなたにとって大切なものです。
かつて私は「自分への憎しみ」に執着していました。
今でこそ
その執着は手放せましたが、
決して能動的に「手放した」ということではなく、
あるとき「気が付けば手放していた」というほうが正確な言いかたです。
そこにたどり着くまでには、
自分の思いを徹底的に見つめ、自分の心の声を聴き、自分の感情を深く感じ尽くしました。
憎しみの感情に込められた本当の意味に、はっと気づき深く理解し始めたとき、
憎しみは自分への慈しみの感情に変化しました。
それを契機にさまざまなことが私の中で変化し、
最終的には天命の理解へと変容しました。
(詳しくは「カウンセラー紹介」をごらんください。)
そういった変化の後になってから自分自身を見てみたとき、
憎しみの感情を「手放した」というふうに見えるだけなのです。

また、憎しみから慈しみへ、そして自分の天命への理解に変容した経験から感じるのは、
やはり私の自分への憎しみの感情には、
私にとって肯定的な意図があったということです。
だからこそ簡単には手放せなかったし、
放り投げたり、なかったことにしたりはしなかったのです。
手放した人が、手放せないでいる人に対して一方的にアドバイスをすると、
身もふたもない言いかたになりますが
最終的には「手放しましょう」ということにはなるでしょう。
それでも、
手放すために放り投げるようなやりかたは、決しておすすめしません。
人それぞれいろいろな方法があるとは思います。
お手玉を放るようなしぐさは飽くまでもイメージだと思いますが、
たとえイメージであっても、いいえ、イメージだからこそ、
あなたにとって大切なものを放るようなことはしないでほしいと思います。
大切なものです。大切に扱ってください。
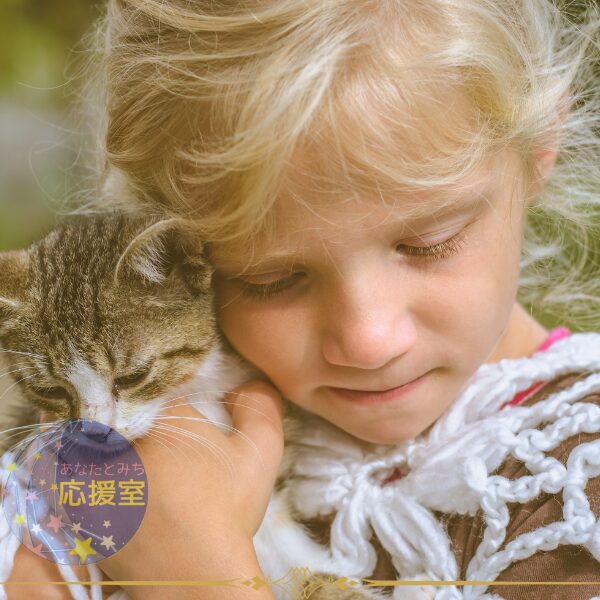
そして
「手放す」ことは「捨てる」ことと同義ではありません。
冒頭でお話しした「手放す」の国語的な意味を思い出してください。
手放して自分のそばから放すことで、息子はどこかへ離れていきました。
そもそも「手放す」なんて言葉を使うことからして、
この息子は大切な存在だということが感じ取れます。
どうでもいい息子なら「手放す」ではなく、「放り出す」、
もっとひどい関係のときは「追い出す」という表現を使うはずです。
ということはつまり「手放す」とは
「大切なものを自分のそばから放す」という意味なのです。
間違っても「捨てる」という意味ではないのです。
捨てるという意味ではないのなら、大切にしたっていいのです。
手放せない思いがあなたにとってどのような肯定的な意図があるのか、
じっくり見つめ、心の声を聴き、自分の心を深く探究してみてください。
その思いの意味に気づいたとき、それは変化を遂げるかもしれません。
また変化を遂げることはなくとも、あなたのそばを自然にすっと離れるかもしれません。
それができないから困ってるんだけど?というあなたへ
それができないから困ってるんだけど……。
そんなあなたには「やらないことにする」という方法をおすすめします。
例えば、イラっとする感情を手放せない、というとき。
イライラすることって、ありますよね。
わたしもあります。
そんなときは、イライラする状況に陥ることがらを、
いったん「やらないことにする」と決心することです。
そして決心したら
自分の「やらないことリスト」に載せておき、それを守りとおすことです。

これも私の例で恐縮ですが、
私のやらないことリストにはけっこう細かいことがたくさん書いてあります。
一例として、「ハンドクリームをケチケチ使うこと」があります(なんとお恥ずかしい……)。
ハンドクリームをケチると、私の場合は手がカサカサになります。
そしてひどいときには指先が切れたりするわけですが、
大した傷ではなくても日常生活はけっこう不便になりますし、見た目も良くありません。
こうなると私の場合は、いやな気分になり、イライラすることが増えるため、
「ハンドクリームをケチケチ使うこと」を「やらないこと」としてリストに載せています。
そして、ハンドクリームをケチケチ使わなくても済むように工夫します。
例えば、かなり手頃な価格のハンドクリームを購入し、使いたいだけの量を使えるようにすること。
また、そもそもそんなに手がカサカサになることを避けようと、洗い物の際は少し面倒でも手袋をはめること。
こうして「ハンドクリームをケチケチ使うこと」をやらないぞ!という決意を守っています。
ほかにも、
「意見を押し付けられること」
「意地悪な人と一緒にいること」
「足を引っ張る人と一緒にいること」
「他人の肩代わりをすること」などなど、数えてみたら34個もリストに書いてありました。
やらないことリストの良いところは
「完全に手放したわけではない」と自分で思えることではないでしょうか。
リストに載っているということは、
自分自身がその項目を意識している、ということにほかなりません。
意識しているということはつまり、完全に手放してはいない、ということになります。

「意見を押し付けられること」「意地悪な人と一緒にいること」
「足を引っ張る人と一緒にいること」「他人の肩代わりをすること」……。
どれも「やらないぞ」と決めてその決意を基本的には守ってはいますが、
時と場合によっては
その決意をゆるめ、
「まあ今回は、やむを得ないから、意見の押し付けも受け入れておこう」とか
「〇〇さんの肩代わりを引き受けようか」とか
許容範囲内で柔軟に対応するようにしています。
(ちなみに代役のすべてを「肩代わり」ととらえているわけではなく、
場合によっては「ぜひとも務めさせていただきます」ということも多々あります。)
やらないことリストに載せた事柄を「やる」ことによって私が抱く暗い感情(イライラとか、ムカムカとか)は、
やはりどこかで私にとって肯定的な意図があるものばかりです。
だからこそ、時と場合によっては決意をゆるめ、
敢えてリストの掲載事項を自分で引き受けることも「あり」なのです。
完全に手放してしまうと、肯定的な側面とその恩恵が私から離れていってしまうことにもなりかねません。
このように、
完全に手放さなくてもとりあえず「やらない」と決めておき、
その決意を適宜ゆるめたり、固く守ったりすればいいのだと、私は思います。
「手放す」……この言葉の、より正確な意味
そして、
大切なものは手放さなくてもいいのです。
本当に大切なものは絶対に手放さないでください。
「手放す」とは
より正確には「大切なものを自分のそばから放す」という意味なのですから……。
(余談ですが、冒頭の国語辞典の息子を手放す例ですが、
もし息子が成人するなどして親元を離れるなら、それは「自立」ですよね。
「自立」と「手放す」とは同義ではありません。念のため申し添えます。)
身もふたもないけれど、最終的にはやっぱり「手放しましょう」
怒り、妬み、恨み、憎しみ……
こういった執着を手放したいけれど手放せない人はたくさんいらっしゃると思います。
職業柄こういった感情を抱くかたのお話を伺う機会が多くありますが、
怒り、妬み、恨み……といった、あなたの心身を傷つける思いは、
最終的には手放したほうがいいと私は思います。
こういった感情に対する執着をすでに手放すことに成功し、
手放し慣れている人からすれば、
結局は「手放しましょう」というシンプルなこのひとことに集約されるのでしょう。
そして
そのひとことには、自己と向き合い内観するプロセスが含まれているはずですが、
今すでに手放し慣れている人だって、過去には苦労してそれを成し遂げた経験があるかもしれません。
ですから
もし今あなたがパッと手放せなくても大丈夫なのです。
手放そうと決意したり、やらないことリストに載せてみるといった工夫のその一歩と、
そして
手放すまでのプロセスが、
あなたにとっては「手放した」という結果以上に大切なのです。
もし、怒り、妬み、憎しみ……といったものを一人では手放せそうもない、
これらの肯定的な意図など分からない、というときは
一人で抱え込まず、その思いを信頼のおけるご友人やご家族に聞いてもらうのはとてもいい手段です。
もし、聞いてくれる人、話せる人が見当たらないときは、カウンセラーを頼ってください。
「あなたとみち応援室」ではあなたがはなせるよう、じっくりとお聴きいたします。
これまでのこと、これからのことをご一緒に考えていきましょう。
この記事があなたのお役にたてましたなら幸いです。



















